かぶとたいぞうです。
冬の太陽ほどありがたいものはありません。
10月下旬の今、札幌の早朝の外気温は6℃くらいまで下がります。我が家は一軒家なので、家の中の温度もけっこう下がります。居間にある温度計では15℃くらいです。
とうぜん石油ストーブをたかなければしのげません。
冬の太陽はストーブより温かい
しかし最近あることを発見しました。
太陽が出ていればストーブは要らないのです。
我が家の居間の東側と南側は大きな出窓になっており、ブラインドを上まであげれば「太陽がいっぱい」です。

実は陽にあたればストーブより温かいのです。
今までどうして気づかなかったんだろう
実際にストーブにあたってみたり、太陽の光にあたってみたりして比較しました。太陽のほうが断然温かいです。今まで気づきませんでした。なんで気づかなかったんでしょう。
さっそく、太陽の光を邪魔しないように庭木の枝を切りました。大きなガラス窓もよく拭きました。ばっちりです。陽が出ると温かいです。
太陽を追って自分が部屋の中を移動すればいい
太陽の直接あたる場所に座ってコーヒーを飲んでいたら、しだいにあつくなって汗が出てくるぐらいです。
太陽の位置が移動したら私の座る位置も移動します。太陽を追って私が家の中を移動するのです。
そうこうしているうちに家の中全体が暖かくなります。
晴れた日の温室効果
晴れた日の太陽がいっぱいの我が家の居間は、温室効果でぐんぐんと室温が上がり、お昼頃には26℃くらいまでになるのです。
そんなこと今までまったく気づきませんでした。
思えば仕事が忙しすぎてそんなことを研究している暇もなかったのです。
仕事ばかりで気づかなかった
以前は仕事が何よりも優先でした。
早朝は冷えるので、起床する前にタイマーでストーブをつけていました。熱いシャワーを浴びながら自動車のエンジンをリモートでかけて車内を温めておきました。
シャワーから出たらストーブの前に座って食事をし、着替えてすぐに家を出ました。
陽のあたる場所を追って家の中を移動するなんてことは考えもしませんでした。
稼いでいたからいいけど
以前は仕事をやってそのぶん稼いでいたから、灯油代も電気代もガソリン代も気になりませんでした。
今はリタイヤ生活なので、少しでもコストを節約しようと考えます。その結果大きな発見ができたのです。
それに、今は家にいて時間があるのでいろいろなことができます。座る場所を移動するのも苦になりません。
仕事をやめるといろいろな発見が
家の中のいろいろな場所に座ると、窓から見える景色もいろいろで新たな発見もあります。長く住んでいた家のはずなのに知らないことがいっぱいあったのです。
太陽が温かいという発見は、コスト節約以上の大きな発見でした。
私にとっては新たな発見でしたが、きっと昔の人はそんなことをとっくに知っていて自然とともに生きていたのだと思います。
街中の太陽
ところで、先日札幌の中心街を散歩していたときにあることに気づきました。
歩いていてとても寒かったので、陽のあたる場所を探したのです。
すると、街の中は背の高いビルばっかりで、陽のあたる場所がどこにもないのです。
ようやく見つけた街中の太陽
この時期は陽が低いから、街中はビルの影ばかりになってしまいます。
ようやく駐車場になっている空き地の前に、陽のあたる場所を見つけました。
そこだけ温かったです。少し傾いた陽に背を向けてしばらくあたりました。
冬の太陽はありがたい
冬の太陽ってこんなに温かいのかと、つくずく思いました。太陽ってすごいなと思いました。ありがたく思いました。
そしてきっと昔の人はこんなことも知っていたんだろうなと思いました。
昔の人が太陽を信仰の対象にした理由も分かったような気がしました。
これからは太陽に感謝する時代
私たちは今までずっと景気が良くてエネルギーの無駄遣いや大量消費に慣れてしまいました。しかしきっと今後の世の中はものを大切にして自然と共に生きる時代に戻るでしょう。
そのときに太陽のありがたさを再認識する人が増えるような気がします。
ごきげんよう。
【関連性の高い記事】
この記事があなたのお役に立った場合、下の「いいね!」をクリックして頂けると、たいへんはげみになります。
【あわせて読みたい】
同じカテゴリーの最新記事5件
-

【生きかた】感謝する。感謝すれば感謝するほど、もっと感謝しなければならないことになる -

【人生観】自分なんて死んでもいい。自分の人生なんて、どうでもいい人生だ。 子供の頃は常にそう思っていた -

幸福はこちらから求めて求められるものではない。ただ楽しい気持を養い育てて、幸福を招き寄せる用意をする外はない(菜根譚) -
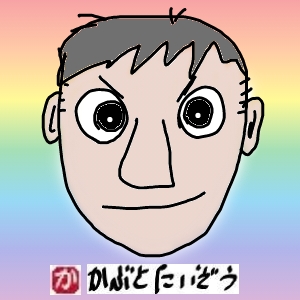
【2026年元旦の挨拶に代えて】心の中で想い描いたイメージは、いつか必ず実現する -

【言葉と行動】相手は自分の言葉より自分の態度や行動を見ている。もし自分の真意が相手に伝わらないのなら
「カブとタイ」をいつもお読みいただき、まことにありがとうございます。
著者かぶとたいぞう拝。
記事のカテゴリー/タグ情報
